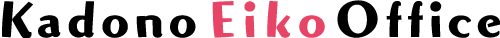私の本に「ごちそうびっくりばこ」というのがあります。奇妙なごちそうがいっぱいでてきます。暑くて食欲があまりないときですので、今回の角野さんちの晩ごはんは、この奇妙なごちそうの一つをご紹介しましよう。ちょっと長いけど、読んでくださいね。
わたしには放浪研究家という妙な職業の友だちがいます。「どんな仕事をするの?」とたずねると、「ほうぽう、うろちょろ歩きまわること」っていう答えがかえってきました。「へんな職業ね」っていったら、「そう、君のくいしんぽやと同じぐらいね」と、わらいました。それからちょっとえらそうに、「かならずなにかしら発見があるからね」って胸をそらせました。
「それじゃ、めずらしいごちそうの発見もあるでしょ」
「もち、めずらしくなくちゃ、ぽくはごちそうとは呼ぼないね」
かれはそこでいっそう胸をそらせました。
「ねえ、おしえて、どんなごちそうに出会ったの?」
わたしはとびつくようにききました。
「そうだねえ、とびきりめずらしいといえぽ……、あのソーダ水なんか……。でも、飲み物はごちそうとはいわないかい?」
「いいえ、りっぱにごちそうだわ」
「あるとき、スイスの山あいの村の、小川にそった道を散歩していると、すぐ足もとに小さなビンが流れてきて止まった。手にとってみると、そのビンにはきっちりとコルクのせんがしてあって、中に手紙が入っていた。ほら、よく海なんかでこんな遊びをするだろ。手紙を入れてビンを流すと、わすれたころになって、とんでもない遠いところから返事がきたりする……。でも、ちょっとへんだった。この小川はすぐ目とはなの先の氷河からとけだした水が流れたものだったから、このびんはそんなに遠くから流れてきたものではないはずだ、と思った。きっと近くの子どものあそびだと、もう一度なにげなくのぞくと、なにかがかすかに光っている。ぽくはいそいでコルクをはずして、なかの手紙を読んでみた」
『地球のみなさま、おおいなる悲しみをもってお別れのごあいさつを申し上げます。
思えばわたしの一生の願いは、宇宙と出会うという、ただその一点にあったのでした。その願いはかなえられました。あまりのうれしさに、わたしは時のたつのをわすれ、帰りのロケットに乗りおくれてしまったのです。
このうえは、あれほどあこがれていた宇宙のまっただ中でしばしの時をすごし、命を終わる……。地上に心をのこす家族もいないわたしには、それでもう十分だと思われました。のこされた時間を十二分に楽しもうと思ったのでした。
ところがあれほど美しいと思っていた天体がとっぜん、まったくとっぜん、ぽろぽろと色あせたものに変わってしまったのです。地上にあって毎夜、っまさき立ちし、首がっかれるほど顔を上にむけて、なにかあるかな、なにが見えるかな、とながめたときのあのわくわくするような宇宙の魔力を、わたしの心はもはや感じることができなくなってしまっていたのです。
さて、もうあまり時間はのこされていません。わたしのいる星の海と、地上のどこかの海べとがっながっているという、ありえないことを、はかなく願って、子どものころ遊んだように、このビンを流してみましょう。中には、天体をさまよう一つの魂のあかしとして、星くずを一つ入れておきます。水をそそいで星の海をしのんでください。
では……さようなら』
放浪研究家はそこまで話すと、目をしばしばさせながら、空のむこうをじっと見上げました。
「それから、ぽくは……」
かれは小さな声でいいました。
「ちょっと見たのではただの石ころにしか見えない星くずをコップに入れて、川の水を入れてみた」
「それで?」
わたしはおもわず乗り出しました。
「コップの中は、たちまちきらめく星空に変わった。水は深いあい色になり、星くずからは小さな泡があとからあとからあがると、それがみんな星の形になって光り出したのだ。あわいピンクやら、レモン色やメロン色にね。その美しいこと。ぼくはすぐさま心に決めた。つぎの放浪先はこの星空のなかだ……ってね」
「それで行ったの?」
わたしはもう一度乗り出しました。
「いや、そう思ったとたん、ぽくはあわててコップのなかみを飲みほしちゃったよ。宇宙の魔力をぽくの腹のなかに入れて、たのしむことにしたのさ。行かないほうがいいと思ってね」
「それで、どんな味だったの?」
すると、かれはにっこりわらっていいました。
「そりゃ、すごいよ。なんたって星空をからだのなかに流しこんだんだからね」
そのとき、わたしはかれの目のなかで、星が三つほどメロン色に光ったような気がしました。