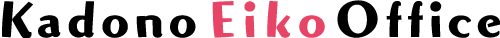私の本に「ごちそうびっくり箱」というのがあります。奇妙なごちそうがいっぱいでてきます。今回の角野さんちの晩ごはんは、この奇妙なごちそうの一つをご紹介しましよう。ちょっと長いけど、読んでくださいね。
わたしがある国の貴族の館ではたらいていたときのことです。わたしのご主人さまは、もも色のアネモネの花のように美しいおじょうさまでした。でも、青い血が流れているといわれる貴族の出らしく、ちょっとぼかり風変わりなお方でした。どう風変わりかというと、足の先から頭のてっぺんまで、朝からそのつぎの朝まで、それはもう気取りっばなしなのです。いびきだってコロラチュラソプラノなら、寝言はまけじと、メゾソプラノ。そばできくと、ミラノのスカラ座にいる心地がいたしました。たとえぼ、わたしになさる朝のごあいさつだって、こんな調子です。
「おお、ナナよ。日はのぼり、小鳥さえずり、うるわしの朝、おはようさま」
十八というお年ごろですからむりもないのですが、これではちょっとやりすぎ、わたしはとても疲れてしまうのでした。
ところでその気取りようは、なんといってもお食事のときが最高でした。たらんとした絹のドレスを着て、一二三、一二三……ワルツのステップをふんで食堂にお出ましになるのです。そして、こんなことをおっしゃったりするのです。
「おお、ナナよ。グリンピースとは、なぜこんなに大きいのか。わたしのこの小さき口には入らぬわ」
しようがないので、わたしがお豆を十文字に切ってさしあげると、ほんとうはがまかえるだって降参するほど大きな口のはずなのに、先っちょだけピチョッとあけて、ピチピチとめしあがるのでした。それからきまって、うっとりと詩を口ずさまれるのです。こんなふうに……。
「地の中より生まれし 青き豆よ
切りさかれて さらに青ざめて 青き豆よ
いこえ わが腹の底で」
そんなとき、わたしはそれこそ、わが腹の底から思いました。
一度でいいから、あの口が、はじからはじまでぱかっとひらくとこ、みてみたい、そんなあ-る日、コックが急病になり、かわりにわたしが夕食を作ることになりました。これはチャンスです。
さっそくスペアリブとよばれている、肉がちょびっとしかついていない、ぶたのあばら骨を一ダースばかり買ってくると、しょうがとニンニクのすったもの、おしょうゆにトマトヶチャップ、とんがらし少々、酢少々、砂糖少々、ぶどう酒をどぶどぶと入れたなかにしばらくつけこんだあと、遠火でじわじわと焼きあげました。
おじょうさまは、ところどころこげ目のついた、さびたナイフのような肉をみると、「ひー」とちいさく悲鳴をあげ、
「なんと巨大な肉よ。わが□、ひきさかれん」
といって、気をうしなってしまわれました。わたしはあわてて、そのほっぺたをたたいて、申し上げました。
「ご心配なく、その小さなお口をお肉にピチョとつけてくださりさえすれば、ちゃんとめしあがれますですよ」
根がすなおなおじょうさまは、こわごわ首をのばし、いわれたとおりにピチョ。わたしは思わず目をつぶり、それからそっとあけたとき見たものは!
ぱかっと、みごとにはじからはじまであいた、おじょうさまの大きな口。両手ににぎりしめたあぼら骨にかぶりつく、オオカミのような歯。そのすき間からは、荒い息づかいといっしょに、こんなことばがとび出してきました。
「うひー、なんと小さな肉よ。わが口、ものたりん」
またたくまに一ダース食べおえたおじょうさまは、いつものくせで詩を□ずさみはじめました。
「あこがれ あばら骨 あぶりあぶり
あばら骨 わが望み もっともっとおかわり
わが願い もっともっと大きなお口」
わたしは成功をいわって、ピューツと口笛をふき上げました。でも、やっぱり、とてもつかれました。
「ごちそうびっくり箱(絵・西村宗 現在は手に入りません)」より